最近、AI系のツールってたくさん出てきていて、正直どれを使えばいいか迷いますよね。
私自身、ChatGPTやNotion AIなんかも触ってきたんですが、ある日ふと見つけたのがこの「NotebookLM」。
Googleが開発しているツールで、「手元のノートや資料を読み込んで、そこから質問に答えてくれる」っていうちょっと変わったアプローチに惹かれました。
「これ、医療系の資料とか自分のまとめたノートを活かすのに使えるかも?」って思ったのがきっかけで、実際に使ってみたらなかなか面白い!
というわけで今回は、NotebookLMの特徴や使い方、他のAIツールとの違いについて、カジュアルに&ちょっと専門的な視点も交えてご紹介してみます。
NotebookLMとは?(何ができるの?)
最近じわじわ話題になってきた「NotebookLM(ノートブック・エルエム)」、名前は聞いたことあるけど、何ができるの?って思ってる人、多いと思います。実はこれ、Google製のAIノートサポートツールなんです。
ざっくり言うと、
「自分がアップロードしたノートや資料をもとに、AIが内容を理解して質問に答えてくれる」っていう仕組み。
たとえば、こんなことができます:
- アップロードしたPDFやGoogleドキュメントの中身を要約してくれる
- その資料の中から「〇〇って何?」みたいな質問に答えてくれる
- 複数の資料をまたいだ質問にも対応(例:資料Aと資料Bの違いは?)
- キーワードや文献の抽出、簡易な比較もできる
これ、ChatGPTやNotion AIとも似てるようでちょっと違うのがポイント。NotebookLMの特徴は、「手元にある資料」にAIの注意がしっかり向くこと。
つまり、自分のドキュメントが“教科書”になるんです。
実際に使ってみると、「このファイルを読み込んでる感」がすごくあって、知識の幅をAI任せにしすぎず、手持ちのデータをちゃんと活かせるっていう安心感があります。
利用条件・料金について
NotebookLMは、現時点では無料で利用できます!(2025年4月現在)
利用にはGoogleアカウントが必要です。お持ちのGoogleアカウントでログインするだけで、追加の申し込みや課金なしにすぐ始められます。
さらに、2024年6月から日本語にも対応し、インターフェースやサポートが日本語で利用できるようになりました。これにより、英語が苦手な方でも安心して利用できます。詳しくは公式ブログの記事も参考になります。
ただし、以下の点にご注意ください:
- サービス内容や料金体系は将来的に変更される可能性があります。
- 最新情報は公式サイトやGoogleの発表を確認することをおすすめします。
実際の使い方:できること・できないこと
NotebookLMを初めて使うときは、まず「ノートブック(Notebook)」をひとつ作成します。そこにPDFやGoogleドキュメントなどの資料をアップロードしたりリンクさせたりして、AIがそれを読んだうえで質問に答えてくれる、という流れです。
使い方はとてもシンプルで、直感的。具体的には、以下のようなことができます:
- 資料の内容を要約(「この文書のポイントは?」と聞けばOK)
- 内容に関する質問に答える(例:「この薬の作用機序は?」「この文献では何が結論?」)
- 複数の資料をまたいだ比較や整理(例:「A文献とB文献の違いは?」)
- 特定キーワードやトピックに関する抜き出し
感覚的には、「自分専用のAI文献ナビゲーター」って感じ。特に医療や学術分野で、情報量が多い文献やレポートを扱う人にはかなり便利です。
一方で、「ここはまだちょっと苦手かな…」と感じる部分もありました:
- 文書構成が複雑なPDFだと、うまく読み取れない場合がある
- 日本語対応はされているが、要約や応答が少し曖昧なこともある
- Web検索はできない(あくまで「アップロードされた資料」ベース)
- ノート間の情報連携はできず、1つのノート内で完結している
とはいえ、資料の読み込み精度や回答の自然さはどんどん進化していて、Googleの開発力を感じます。
自分の手元にある資料をちゃんと活用したい人にとっては、「これこれ!こういうの欲しかったやつ!」ってなるはず。
ChatGPTなど他ツールとの違い
NotebookLMって、パッと見「ChatGPTとかNotion AIと何が違うの?」と思う人も多いと思います。実際、私も最初はそうでした。
でも、使ってみると目的と使い勝手がけっこう違う。以下にざっくり比較してみました:
| ツール名 | 特徴・用途 |
|---|---|
| NotebookLM | アップロードした資料をもとに回答・要約。 「自分のノートを読み込んでくれるAI」的な存在。 |
| ChatGPT | 広範な知識で質問に答える。 資料アップロードもできるが、情報源は限定しにくい。 |
| Notion AI | ノートやタスク整理の補助に強い。 Notion上の情報を使って要約や執筆補助。 |
NotebookLMの最大の強みは、やっぱり「指定した資料だけをベースにしてくれる」安心感。ChatGPTだと情報源がどこか分からないことがあるけど、NotebookLMは「このドキュメントの中で答えてね!」って感じで使えるのがポイント。
一方で、ChatGPTのように柔軟な発想や文章生成力はやや弱め。情報の“創造”というよりは、“整理と理解”が得意なタイプです。
それぞれ得意分野が違うので、うまく使い分けるのが一番!
ヘルスケア企業の社員としての活用アイデア
私は現在、ヘルスケア関連の企業で働いているんですが、NotebookLMを使ってみて「これは実務にもかなり使えるかも」と感じた場面がいくつかありました。
以下は、ヘルスケア業界の業務で活用できそうな具体的なアイデアです:
- 業界レポートや調査資料の要約
市場動向レポートや厚労省の公開資料、業界分析PDFをアップして、要点を抽出・要約してもらう。 - プロジェクト資料の横断的整理
複数の会議資料や経緯メモをまとめてノートに入れ、過去の方針や現在の課題を整理・確認する。 - 製品情報・サービス比較の補助
自社と競合の製品仕様書、提案書、QA資料などを読み込ませて、違いや特徴を整理させる。 - 社内教育・ナレッジ活用
社内マニュアルやトレーニング資料をノート化して、新人からの質問に対する答えを自動生成する。
とくにヘルスケア業界は、情報量が膨大で、しかも専門性が高いという特徴があります。NotebookLMは「自分で読み込ませた資料しか参照しない」ので、業界特有の内容もズレなく対応してくれるのが助かります。
AIに頼るというよりは、自分の情報整理や理解を後押ししてくれる相棒、そんな感じのツールです。
まとめ:おすすめできる人・今後の展望
NotebookLMは、ChatGPTのような“万能なAIアシスタント”とは少し違って、「手持ちの資料をしっかり読み込んでくれる賢いノートパートナー」という感じのツールでした。
特におすすめできるのは、こんな人たち:
- 業務で大量の資料を読む機会がある人(医療・研究・教育・マーケなど)
- 自分の手元にあるPDFやドキュメントを活かしたい人
- 検索よりも「今ある情報を深く理解したい」と思っている人
今後さらに、ノート間の連携や、要約精度の向上、多言語対応の拡充なども期待されています。Google製という安心感もあり、企業利用や教育分野での活用も進んでいきそうですね。
個人的には、「AIとの協働」がもっと当たり前になっていく中で、こういう“ドキュメント特化型AI”はひとつの鍵になると感じています。
気になった方は、ぜひ一度触ってみてください。無料ですし、自分のノートを読み込んでくれる感覚はちょっと感動モノです!
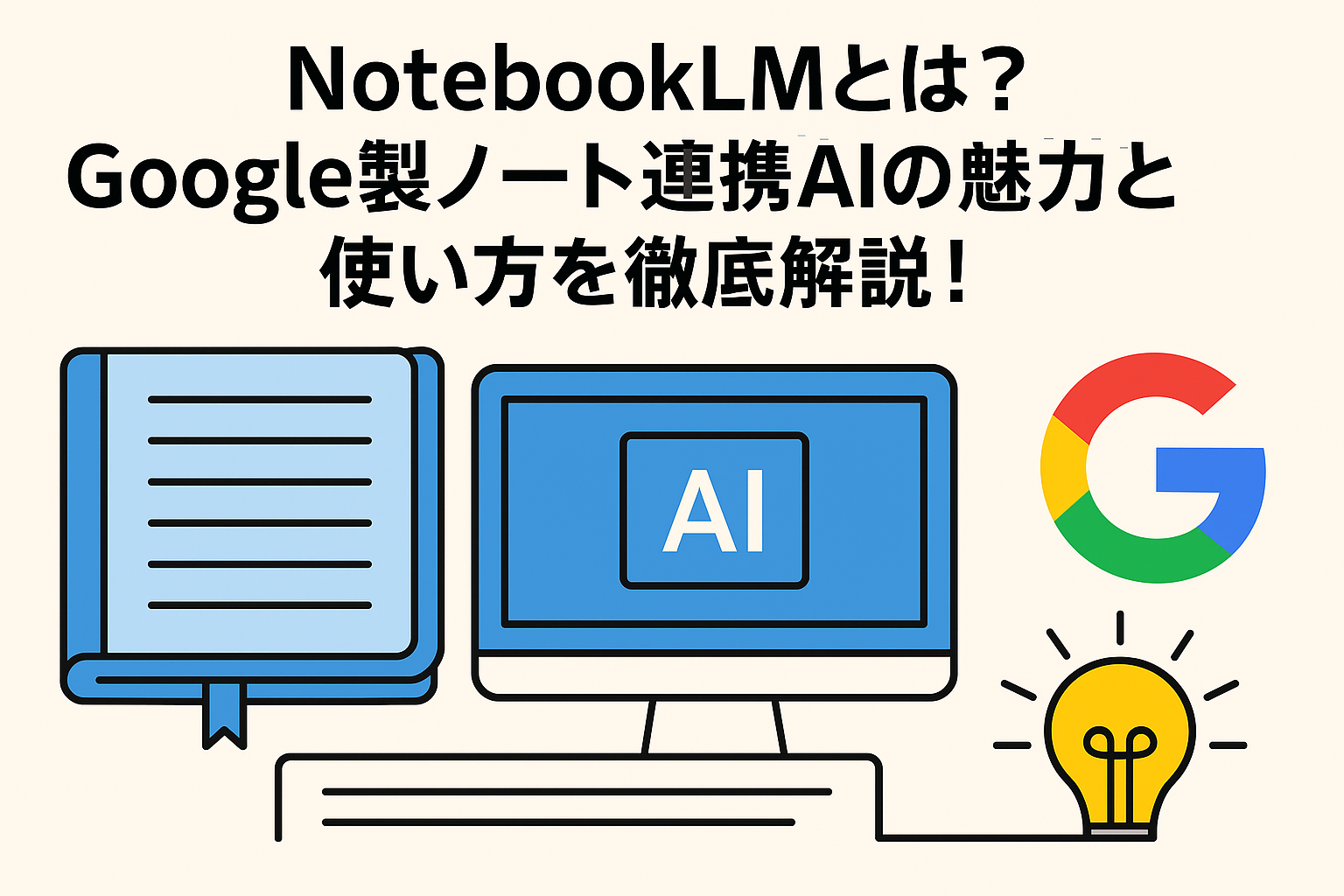

コメント